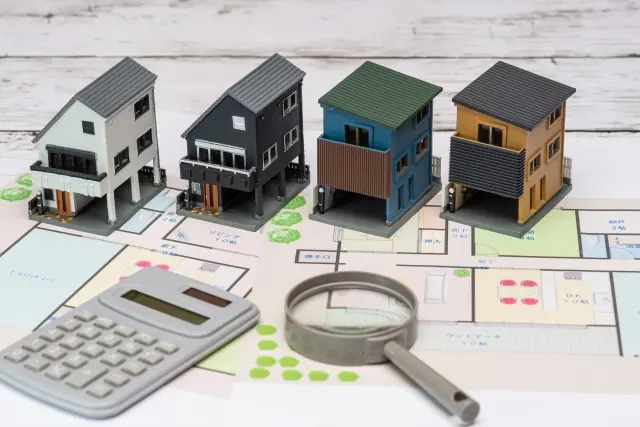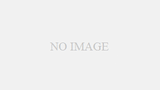空家の問題はとらえ方によってこんなにも異なるのかと恐くなるような立ち位置の本だった。
著者は建築学会の偉い人のようだ。
建築屋さんが見ているのは使われていない「箱」だ。
私のような不動産屋は筑われていない「土地」の問題と考えていた。
もし、こうした建築系の人が空家問題の解決の主流なら空恐ろしいように思う。
理由は以下に述べる。
少子化の傾向は今のところ止めるすべはなく、言ってみれば自然減みたいなものなので、バランスの取れたところで均衡すると思っている。
今少子化が問題だと言っているのは人口のバランスが悪く、高齢者で労働人口から外れて、医療や介護で費用がかさむ世代(それは当然なのでそのことを批判するものではない)に対して実際に負担する世代が少なくなって制度維持が困難になりそうなことを問題視しているからだろう。
よく考えてみれば団塊の世代を含む高齢者は、たくさん働いて資産を増やし世代として貯金がたくさんある世代で、たくさん作った資産(例えば日本の対外債権の金額はまだ世界一だろう)を食いつぶせば何とかなる。
まあそのあとの世代はまた何もないところからってわけにもいかず大変なことは間違いないだろうが、「人口は減る」のだから空家は増加するに決まってるのだ。
その空いたスペースをのんきにも空間資源とか言って維持しようとすることがもはや困難だから空家の問題は深刻なのだということがどっかに行ってしまっている。
確かに都市部のオフィスや倉庫を住宅にコンバージョンしたり、地方都市における駅を中心とした旧市街地の活性化も悪くない。
しかしそれはむしろ、需要と供給のミスマッチ、ないしは必要なインフラの整備に関してのミスであって、本書においても何度も出てくる言葉通り「遊び」でしかないと思う。
人口が減って、必要なスペースが本来小さくなるということは逆に言えば無駄なスペースを維持することは困難になるという前提で考えなければならないだろう。
全国どこでも電気も水道も下水もなどできるはずもなく、通信環境にしてもどこでも平等などできるはずがないのだ。
もし、減少する人口を外国人の移民などで補うとしたならどのようにすべきか。
言い換えると「遊び」で本書でいう「空間資源」をリノベーションによって活用するというのは、個別に見れば素晴らしいことかもしれないが全体としては合成の誤謬に陥る可能性が高いと思っている。
地方に子供が増える、確かにいいことだろう。
だが義務教育は子供がいればどのようにコストがかかろうと行う前提が変わらなければ、むしろ全体としては不経済だ。
道路・橋・水道・下水すべてわずか数人の住民のために維持しなければいかないのか。
そのコストは受益者負担でしか今後は賄えないのではないか。
地方都市における活用されていない建物を利用する物語は、美しく建築家は仕事に満足を覚えるだろう。
果たしてそれは我々の直面している「空家」問題の解決になるのか。
僕にはそうは思えない。
この問題はまだもう少し考えていきたい。
2019/09/17